ネットや書籍で「読みやすい文章を書くためのテクニック」を調べました
「キーワードうんぬん」「魅力的な文章」については、余裕がありません💦
目標は「わかりやすく・読みやすい記事」です
目標を達成すべく、まずは調べた内容をまとめました
ウェブの特性を考慮
紙媒体のときと異なる「ブログ読者の行動」
- 流し読みが基本です
- どのページから読むか決まっていません
- 読むためには縦スクロールが必要です
ブログ特有のおすすめの書き方
- 余白を取り入れます
- 画像や装飾を利用します
- 「」や箇条書きを利用します
- 適切な場所にリンクをつけます
- 1文はできるだけ短くします
段落と改行
スクロールで画面を追うことは、ストレスです
「読みやすいこと」が大切です
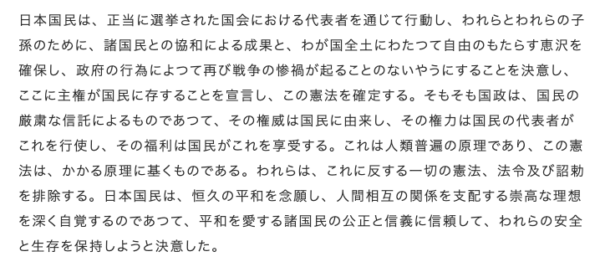
「改行」「段落」がない文章
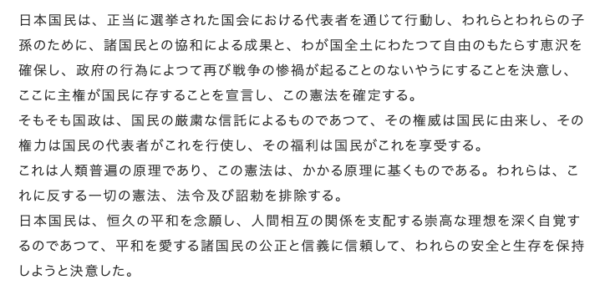
「改行」だけの文章
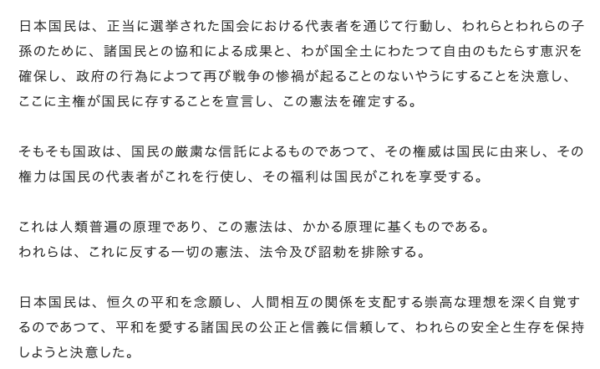
「改行」「段落」がある文章
- 改行
- 文章を区切って行を変えること
- 段落
- 1字分を下げて書きはじめる1区切り
余白があると、読みやすくなります
見た目を考えた「改行」「段落」を入れましょう
漢字はひらく
漢字が多い文章は、堅苦しく読みづらく感じます
漢字は全体の20%~30%程度にします
漢字で書ける語句をひらがなで書くことを「ひらく」といい、「短時間で意味を理解できるそうです
お招き頂き、誠に有難う御座いました。
お招きいただき、誠にありがとうございました。
「ひらく漢字」のたとえ
- 例えば
- たとえば
- 必ず
- かならず
- 最も
- もっとも
- して下さい
- してください
- お勧め
- おすすめ
- 出来る
- できる
- 詳しく
- くわしく
- 分かる
- わかる
- 良い
- よい
- と言う事
- ということ
- ~の時
- ~のとき
- 為
- ため
- 他
- ほか
- 又
- また
- 様な
- ような
- 大変
- たいへん
画像や装飾を使う
伝えたい内容を「可視化」「視覚化」できれば、一瞬で情報を伝えることができます

- 可視化
- 目には見えない物や現象を、見て分かりやすくすること
- 視覚化
- 考えや伝えたいことを、見てわかるような形に示す
- インフォグラフィック
- 情報を視覚で表現し、簡単に早く伝える手法
「視覚で情報を伝える」といっても、「情報集めて整理する」「素材を用意して編集する」作業は、難しそうです
「Canva」を使うと「素材を用意して編集する」ことは簡単です
「Canva」はWebブラウザで使用できるデザイン作成ツールです
(参考)「アカウント作成や基本操作」「グラフの作り方など」を記事にしています
「」や箇条書きを使う
りんごとみかんとバナナ
「りんご」「みかん」「バナナ」
- りんご
- みかん
- バナナ
削る
「周りくどい言い回し」や「詳細すぎる説明」は削って、スッキリすることが大切です
なにげなく使っている言葉でも、不要な単語や文節があります
意味が通じることは詳細に書かない
ウェブサイトのログイン画面で、ログインしてください
ウェブサイトにログインしてください
変更内容を保存します
変更を保存します
不要な修飾語を削る
これは、明らかに、今までで食べた中で、絶賛に値する、一番美味しいラーメンです
これは、一番美味しいラーメンです
なくても意味が通る語句は削る
- 「〜という」
- 「〜のような」
- 「〜といった」
- 「基本的に」
- 「一般的に」
など
基本的に、わたしは早起きです
わたしは早起きです
*必要な場合もあります(必要な場合の例文:基本的には早起きですが、たまに…)
「〜できます」「〜可能です」を削る
1時間で終えることが可能です
1時間で終わります
「すること」「こと」(形式名詞)を削る
犬は、散歩をすることが好きです
犬は、散歩が好きです
なくても意味が通る接続詞は削る
- 「しかし」
- 「なぜなら」
- 「ゆえに」
など
今日は、学校が休みです。なぜなら、休日だからです。
今日は、学校が休みです。休日だからです。
「削れない接続詞」には大切な役割があります
文書全体が支離滅裂になっている場合は、ほとんどの場合で「文のつなぎ方」接続詞が曖昧だからです
文書全体を読んで、「なにかおかしい!!」と感じたら、接続詞を意識すると論理波状しにくくなるそうです
ただし、接続詞の多用は「うざい文章」になるので、要注意です
具体的に書く
書き手は「なにについて書いたか」を知っています
しかし、書き手が「なに」を省略すると「読者が内容を理解しにくい場合」や「読者によって解釈が変わる場合」があります
言葉の意味は具体的に書く
幅広く使われる動詞を具体化する
司会をする
司会を務める
抽象的な表現を具体化する
改行を入れると、効果的です。
改行を入れると、文章が読みやすくなります。
指している単語を具体的に書く
「前者」「後者」は使わない
1+2の答えは3や11の場合があります、前者は10進数、後者は2進数です。
1+2の答えは3や11の場合があります、3は10進数、11は2進数です。
「あれ」「それ」「これ」はできる限り具体的に書く
「あれ」「それ」「これ」がなにかを、書き手は理解しても、読者はそれがなにかを理解しにくい場合があります。
「あれ」「それ」「これ」がなにかを、書き手は理解しても、読者は「あれ」「それ」「これ」がなにかを理解しにくい場合があります。
会話の相手が空気を読んでくれるため、日本語は主語や目的語はひんぱんに省略されます
しかし、省略は勘違いの原因にもなります
複雑な文章は主語や目的語を書きましょう
友達と映画に行きました。
おもしろかったです。
わたしは友達と映画に行きました。
映画はおもしろかったです。
構成
受動態は避けます
*主語が明らかなときは能動態にします
彼らのチームによって、新しいアプリが開発されました。
彼らのチームが、新しいアプリを開発しました。
単語や文節をつなぐとき
意識しないと主語と述語が離れた文章を作成しがちです
主語と述語は近づけましょう
わたしは、昨日のアルコールが抜けないまま職場に行った。
昨日のアルコールが抜けないまま、わたしは職場に行った。
「修飾語」(どんな・いつ・どこに)は「被修飾語」(説明される文節)の直前におく
わたしは、毎朝、ご飯を食べる前の犬と散歩します。
わたしは、ご飯を食べる前の犬と、毎朝散歩します。
「修飾語」が2つ以上あるときは「長い修飾語」を先に書く
なつかしい、むかし流行ったモノクロの映画
むかし流行ったモノクロの、なつかしい映画
「の」や「と」など「同じ助詞」の連続使用は2回まで
わたしの職場の同じ部署の山田さん
わたしの職場の同じ部署に在籍する山田さん
読点を打ったり、文をつなぐとき
「が」で言葉をつながないようにしましょう
欲張りじいさんは臼を無理やり借りると、自分の家でもちをついてみましたが、出てくるのは石ころばかりで、宝物は出てきません。
欲張りじいさんは、臼を無理やり借りると自分の家でもちをついてみました。
しかし、出てくるのは石ころばかりで宝物は出てきません。
読点「、」の位置で意味が変わるので、正しい位置に打ちましょう
父は泣きながら、嫁に行く娘を見送った。 (泣いているのは、お父さん)
父は、泣きながら嫁に行く娘を見送った。 (泣いているのは、娘さん)
文末に同じ語句の連続は避けます
むかし、むかし、ある所におじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんは山へしば刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。
おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃が流れてきました。
「結論」「主張」「全体像」「目的」は先に書きます
おすすめの動画配信サービスをご紹介します。
「Amazon Prime Video」「U-NEXT」「Hulu」「FODプレミアム」です。
「Amazon Prime Video」とは・・・
「U-NEXT」とは・・・
おかしな日本語の使用は避ける^^;
重言の使用は避けましょう
重言は「馬から落馬する」のように、意味が同じ語句を繰り返す言い方です
| NG | OK |
| 後で後悔する | 後悔する |
| いちばん最後に演技した | 最後に演技した |
| いまだに未完成 | 未完成 |
| 違和感を感じる | 違和感がある |
| 採用の内定が決まった | 採用が内定した |
| IT技術 | IT |
| そもそもの発端は | 発端は |
「ら抜き言葉」は避けましょう
| NG | OK |
| 見れる | 見られる |
| 食べれる | 食べられる |
| 来れる | 来られる |
| 決めれる | 決められる |
| 着れる | 着られる |
| 起きれる | 起きられる |
「〜たり〜たり」と連続で用いるのが正しい用法です
本を読んだり音楽を聴いて過ごしています。
本を読んだり音楽を聴いたりして過ごしています。
誤字脱字にも注意しましょう
間違い探しは大変ですが、無料の校正ツールを使えば楽です
「文章の貼り付け」か「URLの読み込み」でチェックします
書くときに意識してみるといいかも
- 遠回しな表現になっていませんか?
- もっとシンプルな言い回しができるかも?
- 数年前の自分に伝えるつもりで書くといいかも
- 音読してみるといいかも
意識しすぎると、つかれて書けなくなりそうですw
書くことが苦手なのに、ブログを書いている理由はアウトプットのためです
でも、もしかしたら「誰かのお役に立てるかも」という気持ちはモチベーションになります😊
